
マストのミッションはこなしたが、求めていた「それ以上」を得ることはできなかった。廣山望監督に率いられたU-17日本代表の挑戦は、“アジア8強”で閉幕を迎えた。
AFC U17アジアカップサウジアラビア2025は同年11月に行われるU-17W杯の予選を兼ねた大会である。この世界大会は今回から出場国を大幅に拡充し、48チームが参加することになった。このため、アジアからの出場枠も4から8へと拡大されていた。
この変更に伴い、これまで「ベスト4で世界切符」だったのが、「ベスト8(つまりグループリーグ突破)で世界切符」とハードルが大きく変わった。ルールが変われば、当然ながら戦い方も変わってくる。
過去大会にコーチとして参加している廣山監督も、そうした変化を実感したひとりだ。「グループリーグの戦いは、これまでの大会とまるで違っていました」と振り返るとおりだ。
従来の大会では、日本を含めたいわゆる“アジアの強豪”は準々決勝に照準を合わせて大会を戦う傾向が強かった。ただ、今大会はグループリーグからエンジン全開のハードな攻防が連続。これまで世界大会をノーチャンスと捉えていたような国々が「(世界大会に)行けるかもしれないと、より思うようになった」(廣山監督)ことも影響しているだろう。
実際、日本の入ったグループBは1勝1分1敗の勝点4で3チームが並び、最下位のベトナムにしても3引き分けの勝点3という混戦模様だった。従来型の「グループリーグでエンジンを掛けていき、準々決勝で100%」のようなイメージで戦っていると、いずれ「敗退」の2文字に直面しかねない。
一方で中2日の連戦、今回は高地開催という特殊性もあった中で、体力面を考えてのマネジメントはやはり不可欠だ。今回は準々決勝で体力面を考えて大幅なメンバー変更に至ったが、そもそも第3戦でしっかり勝ち切れる状態にするためにも、第2戦の使い方をキーファクターとして捉え直すべきではとも感じた。
もちろん、今回8強に終わったことにより、次回大会は日本が組み合わせ抽選の第1ポットから外れることになると思われるため、今回とは違った対戦順になるだろう。ただ、どういう順番で対戦するにしても、「グループリーグ第3戦に100%をぶつけられる」状態にしておくのはマストのように感じられた。
結果としてグループ1位抜けだったとはいえ、薄氷の結果であったことを楽観的に捉えるべきではないし、個々の課題はもちろんだが、大会をどう捉え、どう戦うべきかという大枠の議論もあっていいだろう。
準々決勝について言えば、1位抜けになったことで開催国のサウジアラビアと当たったことをどう捉えるか。敗れたのだから良くなかったと言うのは簡単だが、異様な雰囲気に包まれたスタジアムでPK戦まで戦い抜いた経験値自体は貴重なもの。敗退についてはシンプルに力不足だったと受け止めるほかない。
もちろん「ここからさらに準決勝、決勝という舞台を戦う中で自信を付けてほしかった」という廣山監督の言葉は本音だろう。ただ、過去にこのチームの合宿に顔を出した日本代表DF冨安健洋や同MF堂安律が話して聞かせてくれたように、「負けた悔しさで成長できる」ことがあるのもこの年代の選手たちだ。
二人とも揃って16歳でアジアでの敗退を経験し、自分へ矢印を向けてプレーをスケールアップさせ、世界舞台で戦える存在へと変わっていった。
幸いにも、この年代の選手たちには、冨安や堂安と同じく“アジア8強での敗退”ながら、半年後に世界大会が待っている。そのための競争も新しく始まり、新たに伸びてくる選手も必ず出てくるだろう。
まずはここからの半年の各大会で、今回のメンバーに入った選手、ケガで外れた選手はもちろん、候補で落ちた選手や、眠れる逸材を含め、「俺を世界大会へ連れて行け!」という選手たちの活躍が数多く観られることを期待しておきたい。
(取材・文 川端暁彦)
●AFC U17アジアカップ2025特集
Source: サッカー日本代表

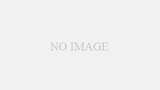

コメント